親の「大丈夫」が生む落とし穴
親として「うちの子は大丈夫」と思いたいのは自然なことです。
子どもの健康や成績、友人関係がまずまず許容範囲内であるように見えると、特に安心するもの。
でも、その「思い込み」が子どもの心のSOSを見逃す原因になることがあります。
「大丈夫」の裏に隠れているリスク。
親子関係をより深めるためのヒントを一緒に探っていきましょう!
親が「うちの子は大丈夫」と思い込む理由

親自身の安心感を保つため
子育て期の親は、とにかく忙しい!
その日常の中で、子どもの全てに気を配るのは難しいでしょう。
「大丈夫」と思い込むことで、問題をディスカウントし、自分の安心感を保ちたくなります。
これは自然な心理ですが、子どもの細かな変化に目を向ける余裕を失ってしまう原因にもなりかねません。
子どもの自己表現の変化
多くの子どもは10代に入ると、自分の感情を隠したり、親に見せないようになります。
一見、学校生活を順調にこなしているように見えても、その裏には不安や悩みを抱えている場合があります。
「今のままで上手くやっている」という表面的な判断が、本質を見逃すきっかけになることがあります。
他人と比べた安心感
友人との子育て談義。
「他の子に比べればうちはマシ」「まあ、そんなものか」という比較意識は、親として抱きがちな感情です。
しかし、他人との比較が増えるほど、自分の子どもの個性や特有の悩みを見逃しやすくなります。
「普通だから大丈夫」と感じることが、SOSのサインを曖昧にしてしまうこともあるのです。
これらの前向きな考え方は親として決して悪いわけではありません。
ただし、子どもが発する小さなサインをキャッチするためには、もう一つの視点をもつ必要があります。
子どもの心のSOSのサインとは?

子どもが心にSOSを抱えているとき、そのサインは意外と小さく、日常に紛れ込んでいることがあります。
以下に、子どもが悩みや困ったことを抱えているのに、親に見逃されがちな具体例を挙げます。
表情や態度が以前と違う
笑顔が減った
無表情になることがある
ため息が増えた
些細なことでイライラする
今までは平気だったことに対して過剰に反応する
親の反抗が増えたりする
学校や習い事の話をしなくなる
それらについて話題を避けるようになった
おざなりにごまかす
健康面での不調を訴える
「頭が痛い」
「お腹が痛い」
「だるい」
のように漠然とした体調不良を頻繁に訴える
親として「これくらいは普通」と片付けず、子どもの些細な変化に敏感になりましょう。
大きな問題を未然に防ぐことができます。
親としてできること

子どもに「安心感」を与える
気になるからと言って、いきなり「最近、何か困ってるの?」と質問されると、子どもは警戒します。
そんなときは、子どもが楽しんでいるゲームや本について関心をもち、子どもから教えてもらってください。
子どもが心を開いて安心して話せる雰囲気を作れます。
結果よりもプロセスを認める言葉を
子どもを大切に育てたご家庭であればあるほど、親の思いに応えようと本心を隠すかもしれません。
例えば塾の成績を褒めたいときは、「成績の順位上がって凄いね!」と結果を評価するよりも、「お母さんが見てない間も自分で努力して頑張ってたんだね!」と本人を認める言葉で伝えましょう。
子どもは親からの期待に追い詰められることなく、自分のペースで成長を目指せるようになります。
自分の不安を子どもに投影しない
あなた自身が過去に経験した失敗や不安。
心理学的には、それを無意識のうちに子どもに投影することが起こりやすいことを知っておきましょう。
自分が失敗したり傷ついたことについては否定的なアドバイスをしがちです。
自分とは別の人間である、その子どもの意思を尊重しながら応援し寄り添う視点が重要です。
子どもと心を通わせる実践のコツ
晩御飯の時間やお風呂、寝る前のひと時にテーマを決めてお話を聴きあう時間を持ってみませんか?
「今日一番うれしかったこと」「一番楽しかった時間」等、もちろん親も話します。
反省会はNG、短時間で負担にならないよう毎日続けることで効果が出てきます。
子どもの気持ちを知るきっかけになり、親の思いを伝える時間にもなります。
このような小さなコミュニケーションが、親子関係をより良いものにしていきます。
まとめと次の一歩
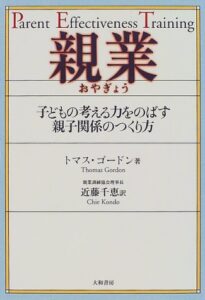
子どもは、親に心配をかけたくないという気持ちから本音を隠すことがあります。
「うちの子は大丈夫」と思い込むのではなく、「今日はどんな一日だった?」と彼らの感情を知ろうとする姿勢を大切にしましょう。
子どもの体験に興味関心を持ち、その心に寄り添うことが、信頼関係を築く第一歩です。
もし今回の記事が気になった方は、さらに実践的な方法を学べる親子のコミュニケーションスキルを学ぶ講座への参加を検討してみてください。
ご一緒に、子どもの心の声に気づき、自立を導く親子関係を築いていきませんか?








